ファミマ「トイレは聞かれても貸しません」清掃代と慰謝料150万円請求の貼り紙が波紋
有料化、公的支援、マナー向上 – 持続可能な仕組みへの模索
今回の貼り紙で店主が訴えた「トイレの有料化」は、問題解決に向けた選択肢の一つとして、以前から議論されてきた。持続可能な仕組みを構築するため、様々な角度からの模索が続いている。
現実味を帯びる「有料化」の議論
SNS上では「有料化に賛成」「むしろ気兼ねなく使える」といった肯定的な意見が多く見られる一方で、「有料化しても維持費には足りないのでは」という指摘もある。実際に、東京・秋葉原の有料トイレは1回100円の料金設定でも運営費を賄えず、赤字分を区が補填しているという事例もある。有料化が根本的な解決策となるかについては、専門家の間でも意見が分かれているのが実情だ。
官民連携による公的支援の可能性
もう一つの道は、行政による公的支援である。過去には神戸市が観光地の民間施設トイレに清掃費などを助成した例や、東京都千代田区が期間限定で協力事業者に費用を補助した「ちよだ安心トイレ」制度などが存在した。コンビニトイレを準公共的なインフラと位置づけ、清掃業務を外部委託し、その費用を自治体が補助するような官民連携モデルを求める声も上がっている。
企業の取り組みと利用者の意識改革
事業者側も手をこまねいているわけではない。ローソンは2022年から、トイレ空間をアートで彩り、利用者にマナー向上を促す「アートトイレ」プロジェクトを展開している。この取り組みにより、実際に清掃・メンテナンスの回数が減少するなどの効果が確認されているという。
しかし、どのような対策を講じても、最終的に不可欠なのは利用者一人ひとりの意識である。「使わせてもらっている」という感謝の気持ちを持ち、きれいに使うこと。そして、可能であれば少額でも商品を購入し、感謝を形にすること。この当たり前の行動の積み重ねが、社会の貴重なインフラを守る最も確実な方法なのかもしれない。
「当たり前」ではないサービス – 利用者と事業者が向き合うべき課題
一店舗の悲痛な叫びから始まった今回の騒動は、コンビニトイレが抱える構造的な問題を社会に突きつけた。それは、もはや個々の店舗の努力や利用者のマナーに訴えかけるだけでは解決できない段階に来ていることを示唆している。
コンビニトイレは、多くの人々にとって「あって当たり前」の存在となった。しかし、その「当たり前」は、加盟店の経済的・精神的な犠牲の上に成り立つ、極めて脆弱な善意のサービスである。この現実から目を背け続ければ、日本中から「貸したくない」トイレがさらに増えていくことは避けられないだろう。事業者、行政、そして私たち利用者一人ひとりが、この便利なサービスをどう維持していくのか、真剣に向き合うべき時が来ている。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]








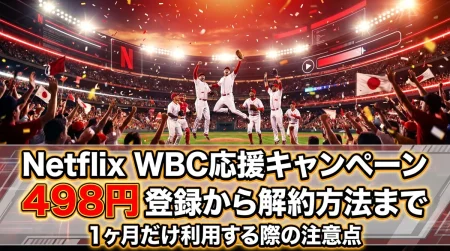










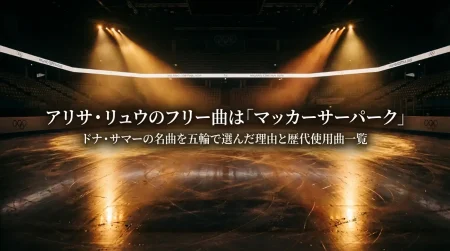
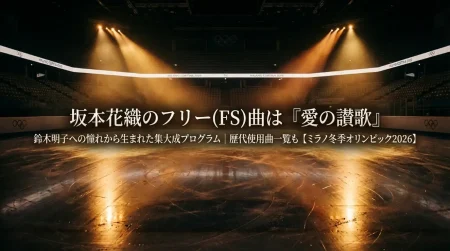
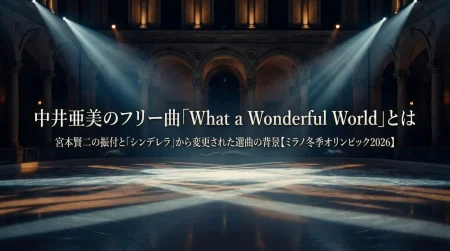




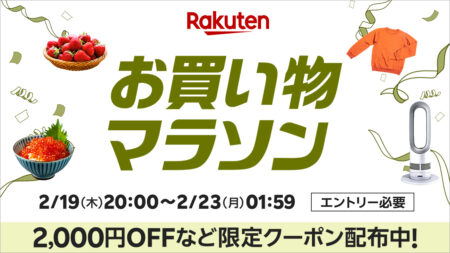


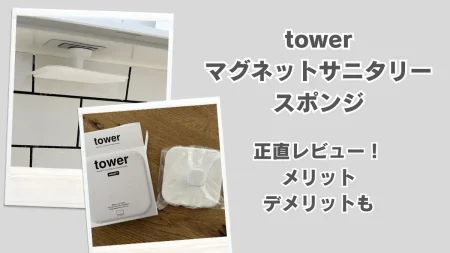
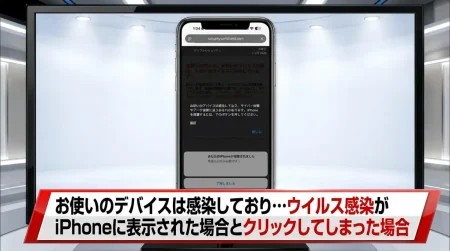

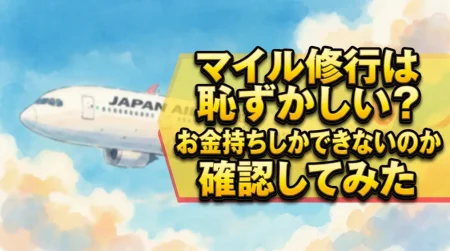
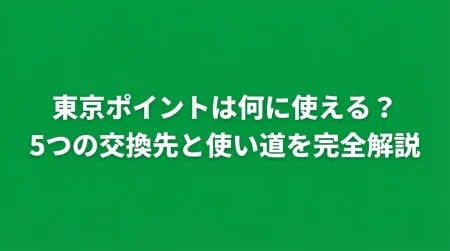

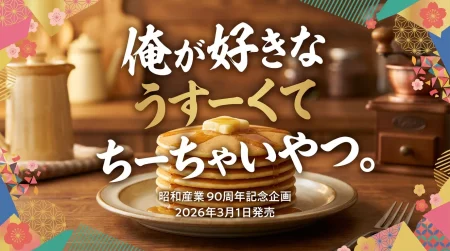






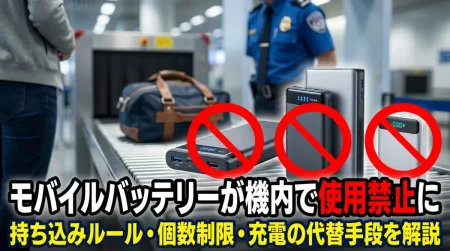














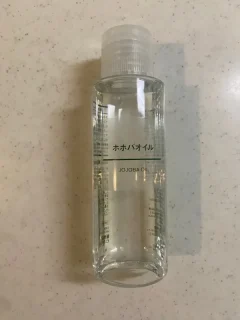

コメントはこちら