近江八幡『日牟禮八幡宮』参拝ガイド|見どころと1900年の歴史を徹底解説

📷写真・📝レビュー提供:やままる
取材・編集:MEDIA DOGS 編集部/ © 2025 MEDIA DOGS
近江八幡の美しい町並みの中心に、どっしりと構える「日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう)」。先日、平日に訪れたのですが、その賑わいにまず驚きました。
この記事では、そんな私の実体験をもとに、日牟禮八幡宮の魅力と、参拝前に知っておきたい1900年の歴史をギュッと凝縮してお伝えします。
日牟禮八幡宮ってどんなところ?基本情報まとめ
日牟禮八幡宮は、滋賀県近江八幡市のまさに中心、風情ある八幡堀のすぐそばに鎮座しています。実は「近江八幡」という市名の由来にもなった、この土地のアイデンティティとも言える古社なんです。
境内は広く、国の選択無形民俗文化財に指定されている二大火祭り「左義長まつり」と「八幡まつり」が奉納される場所としても全国的に有名です。
基本情報(2025/11/11現在)

近江八幡の歴史を見守ってきた荘厳な入口。
- 場所: 滋賀県近江八幡市宮内町257
- アクセス: JR近江八幡駅からバスで「大杉町」または「八幡堀」下車すぐ。車なら名神「竜王IC」から約25分。
- 駐車場: 境内に参拝者用駐車場あり(無料)。ただし祭礼時は規制されるので注意。
- 参拝時間: 境内は24時間自由。授与所は8:30~17:00。
- 公式サイト: https://himure.jp/

タッチパネル式の最新の案内板で、参拝情報や周辺スポットを確認できます。
3分でわかる!日牟禮八幡宮の壮大な歴史
この神社の歴史を知ると、参拝が何倍も面白くなります。約1900年という壮大な歴史を、ポイントだけかいつまんでご紹介しますね。
始まりは神話の時代(131年)
社伝によれば、その始まりはなんと西暦131年。第13代成務天皇が、この地に地主神である大嶋大神(おおしまのおおかみ)を祀ったのが起源とされています。まさに神話の時代から続く、由緒ある場所なんです。
八幡宮としての成立(275年~)
その後、275年に応神天皇がこの地を訪れた際、不思議なことに太陽(日輪)が2つ現れるという吉兆があったとか。そこから「日群之社(ひむれのやしろ)」と名付けられ、八幡宮としての歴史がスタートします。
平安時代の991年には、一条天皇の願いにより、八幡信仰の総本社である宇佐神宮(大分県)から神様をお迎えし、背後の八幡山に「上の社」が創建。のちに山麓に遥拝所として「下の社」が建てられました。
戦国時代、そして近江商人と共に
時代は下り、1585年。豊臣秀次が八幡山城を築城する際に、山の上にあった「上の社」を麓の「下の社」に合祀。これが現在の形につながっています。その後、関ヶ原の戦いの後には徳川家康が武運長久を祈願した記録も残っており、武将からの信仰も篤かったことが伺えます。
江戸時代に入ると、八幡山城の城下町は商業の町として発展。日牟禮八幡宮は、全国を股にかけ活躍した近江商人たちの守護神として、篤い信仰を集めることになりました。
いざ境内へ!私の体験レポート
楼門から拝殿へ – 賑わいと厳かな空気
立派な楼門をくぐると、空気がスッと変わるのを感じます。私が訪れたのは平日でしたが、七五三の時期ということもあり、晴れ着姿の子供たちや家族連れでとても賑わっていました。
手水舎で身を清め、拝殿に向かいます。奉納された酒樽がずらりと並び、地域からの信仰の厚さが伝わってきますね。

ずらりと積み上げられた酒樽は、神事への献上や地域の信仰の厚さを物語っています。

楼門からまっすぐ進むと、立派な「拝殿」があります。多くの参拝者はここで手を合わせ、満足して帰路についていました。

奉納された提灯や絵馬が目を引く、神社の中心となる建物です。

本来の参拝はここまででもOK。ですが、今回私たちは拝殿の奥、本殿の方まで散策をしてみました。



本殿と奥の社を繋ぐような木橋があり、
背後の岩肌と調和して独特の雰囲気を作り出しています。

石灯籠が並び、緑に囲まれた静かな参道は、神聖な空気に満ちています。
苔むす石灯籠と静寂のパワースポット感
奥のエリアに足を踏み入れると、それまでの賑わいが嘘のような静寂に包まれます。木々に囲まれ、苔むした石灯籠が並ぶ参道は、まさに「パワースポット」という言葉がぴったり。

本殿や、学問の神様・菅原道真公を祀る天満宮などの境内社が静かに佇んでいます。ここまで来てこそ、日牟禮八幡宮の持つ本来の神聖な空気を深く感じられるはずです。ぜひ、時間に余裕を持って奥まで散策してみてください。
次のページへ:見どころ満載!境内の注目ポイント






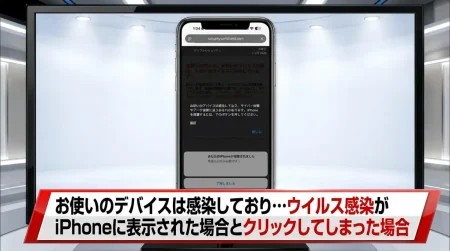














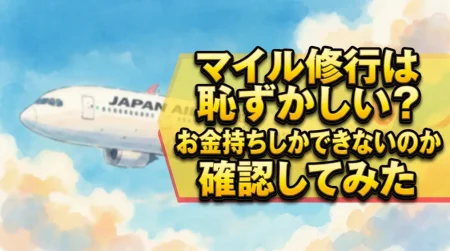
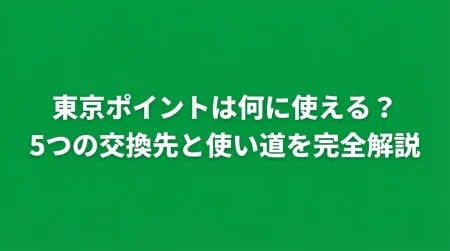






















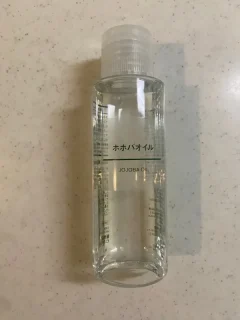


コメントはこちら