函館の台所「中島廉売」探訪記。レトロな雰囲気と人の温かさに触れる午後散歩中島廉売

取材・編集:MEDIA DOGS 編集部/ © 2026 MEDIA DOGS
函館といえば、函館朝市を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、地元の人々が「本当の台所」として愛する場所は、少し離れたところにありました。それが今回訪れた「中島廉売(なかじまれんばい)」です。
私が訪れたのは、平日の午後2時。市場の喧騒が落ち着き、ほとんどのお店がシャッターを下ろしている時間帯でした。「少し来るのが遅かったかな…」と一瞬思いましたが、その静けさの中でこそ感じられる、この場所ならではの温かい魅力と出会うことができたのです。
この記事では、観光ガイドブックには載っていないかもしれない、午後の「中島廉売」のリアルな姿と、そこで感じた人の温かさ、そして散策のヒントをお伝えします。
「中島廉売」ってどんなところ?歴史と名前の由来
大火からの復興が生んだ「市民の台所」
中島廉売は、函館駅から市電で10分ほどの場所に位置する商店街です。その歴史は、1934年(昭和9年)に発生した函館大火に遡ります。市街地の3分の1を焼き尽くしたこの大火で被害を免れた中島町エリアに、数百軒の露店が自然発生的に集まったのが始まりとされています。
「廉売」とは、文字通り「品物を安く売る」こと。その名の通り、新鮮な食材が手頃な価格で手に入ることから、長年にわたり「函館市民の台所」として親しまれてきました。現在も鮮魚店や青果店、精肉店、惣菜店など約100軒のお店が軒を連ね、昭和の面影を色濃く残しています。

地名に刻まれた幕末の歴史
少し歴史を深掘りすると、「中島町」という地名自体にも物語があります。この地名は、幕末の箱館戦争で、旧幕府軍として最後まで新政府軍に抵抗し、この地で壮絶な最期を遂げた武将・中島三郎助に由来しています。市場の近くには「中島三郎助父子最後の地碑」もあり、このエリアが持つ歴史の深さを感じさせます。
【体験レビュー】平日の午後に歩いて感じたリアルな雰囲気
千代台電停からのアクセスと第一印象
2025年10月31日の午後2時、私は函館市電の「千代台」電停で降りました。公式な最寄り駅は一つ手前の「堀川町」のようですが、千代台からも徒歩5分ほど。大きな看板が目印となり、迷うことなく到着できました。
市場に足を踏み入れると、そこはまさに「昔ながらの商店街」。狭い路地にたくさんのお店がひしめき合っていて、そのレトロな雰囲気に一気に引き込まれました。

静かな時間帯だからこそ見えるもの
平日の午後ということもあり、ほとんどのお店はシャッターが閉まっていました。活気ある市場を想像していたので少し残念でしたが、逆に言えば、これが地元の人々の生活リズムに根差した市場である証拠。観光地化されていない、ありのままの姿を見ることができた気がします。
数軒営業していた八百屋さんやたい焼き屋さんには、地元のお客さんらしき人々の姿が。お店の人との何気ない会話が聞こえてきて、とても和やかな空気が流れていました。

閉まっているお店も、その看板や店構えを眺めているだけで十分に楽しめます。一つ一つの店名やデザインに歴史が感じられ、まるで昭和時代にタイムスリップしたかのよう。どんな品物が並び、どんな人々で賑わっていたのだろうと想像が膨らみます。


次ページ:良かった点と気になった点、隣のパン屋の紹介




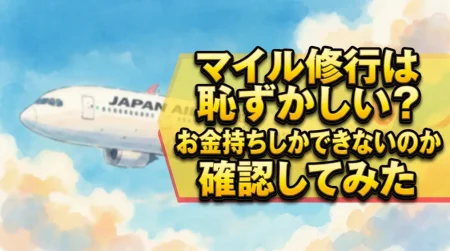
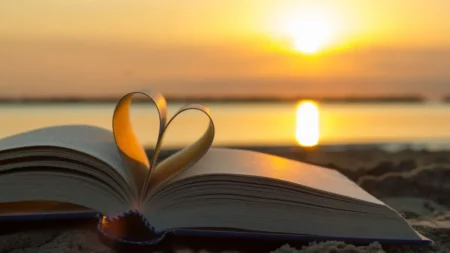









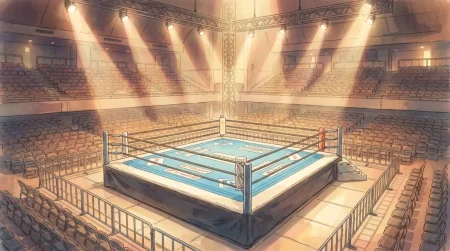





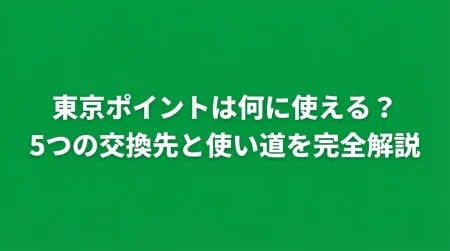





















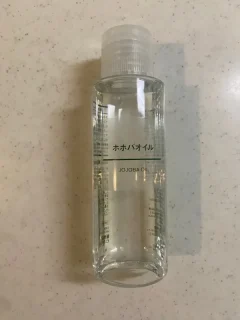


コメントはこちら