フジ清水社長、崖っぷちの船出「この1年が勝負」 巨大組織は本当に変われるか

元タレント中居正広氏を巡る問題に端を発した一連の騒動で、フジテレビは視聴者やスポンサーからの信頼を大きく失墜させた。2025年1月、港浩一前社長らが引責辞任する異常事態の中、後を託されたのが清水賢治新社長である。就任時に「信頼回復なくしてフジテレビに未来はない」と断言し、その後も「この1年間でどこまで本当に変えられるか」と強い決意を語る清水氏。アニメ『ちびまる子ちゃん』の初代プロデューサーとして知られる異色の経歴を持つリーダーは、開局以来の危機にどう立ち向かっているのか。その改革の道のりは、まさに崖っぷちからの船出である。
「人権意識の欠如」「閉鎖的な組織」- 改革はなぜ不可避だったのか
改革が待ったなしだった理由は、2025年3月末に公表された第三者委員会の報告書に凝縮されている。報告書は、問題を「業務の延長線上における性暴力」と断じ、経営陣の低い人権意識と危機管理能力の欠如を厳しく指摘。「セクハラに寛容な企業体質」や「組織の強い同質性・閉鎖性・硬直性」といった根深い病巣を白日の下に晒した。長年トップに君臨した日枝久相談役(当時)の影響下にある「オールド・ボーイズ・ネットワーク」によるガバナンス不全も問題視された。
社会の反応は速く、そして厳しかった。動画撮影を禁じた閉鎖的な記者会見は「保身」「隠蔽体質」との批判を呼び、SNS分析では批判的意見が9割を超える結果となった。トヨタ自動車をはじめとする大手スポンサーのCM出稿停止も相次ぎ、経営を直撃。2026年3月期には営業赤字に転落する見通しとなり、フジテレビは存立の危機に瀕した。追い打ちをかけるように、総務省は「放送に対する国民の信頼を失墜させた」として異例の行政指導に踏み切り、抜本的な改革を迫られたのである。
【核心】清水改革の全貌 – 聖域なき「8つの具体策」と「アクションプラン」
危機的状況を受け、清水新体制が打ち出したのが「フジテレビ再生・改革に向けた8つの具体策」と、それを包含するフジ・メディア・ホールディングス(FMH)の「改革アクションプラン」だ。その中身は、ガバナンス、組織文化、事業戦略の三つの領域にわたる聖域なき改革であった。
1. ガバナンスの抜本的刷新:「オールドボーイズクラブ」の解体
最もメスが入ったのが、ガバナンス体制だ。フジテレビの取締役は22人から11人へと半減させ、FMHでは独立社外取締役が過半数を占める構成に変更。女性取締役比率もFMHで45.5%に達し、平均年齢も約10歳若返らせるなど、多様性の確保を急いだ。象徴的だったのは、40年以上取締役を務めた日枝久氏の退任と、長年続いた相談役・顧問制度の完全廃止である。役員定年制も導入し、特定の個人への権力集中を防ぐ仕組みを構築。さらに、独立社外取締役がトップを務める「リスクポリシー委員会」を新設し、外部の目で人権リスクなどを監督する体制を整えた。
2. 組織文化へのメス:「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却
「社内の一部に『楽しくなければテレビじゃない』を過度に重視した風土が根付いていた」。この反省のもと、旧来の組織風土の象徴とされた「編成局」と「バラエティ制作局」を解体。制作部門を「スタジオ戦略本部」、編成機能を「コンテンツ投資戦略局」へと再編した。また、ハラスメントの温床と指摘された制作側とアナウンサーの従属的な関係を断つため、アナウンス室を「アナウンス局」として独立させ権限を強化。放送法の原点に立ち返り、「公共性」と「社会的責任」を重視する姿勢へと舵を切った。
3. “攻め”の事業改革:「コンテンツカンパニー」への大転換
守りだけでなく、“攻め”の改革も同時に進める。清水社長が掲げるのは、真の「コンテンツカンパニー」への進化だ。「まず放送枠ありきで企画を考える」という従来のモデルから脱却し、良質なIP(知的財産)を創出し、配信、映画、海外展開など多様な出口で収益化する戦略を打ち出した。その実現のため、5年間で2500億円規模という巨額の投資計画を公表。うち1250億円以上をコンテンツ関連に充て、広告収入への依存度を現在の7割から5割に引き下げることを目指す。
次ページ:期待と懐疑の交錯 – 問われる改革の本気度と自浄作用




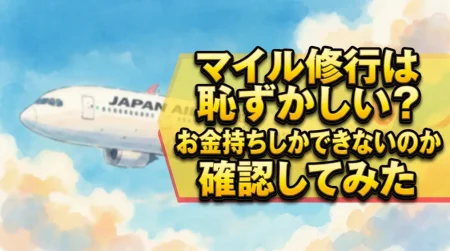
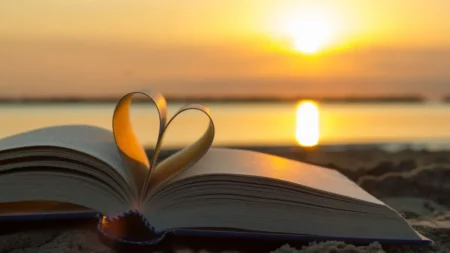









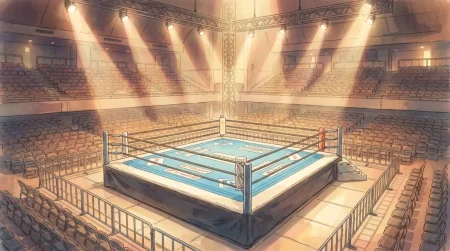





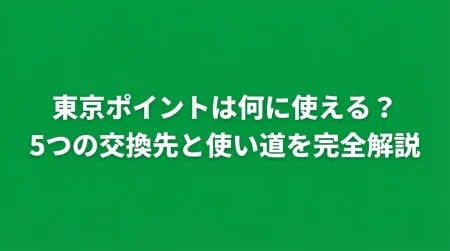





















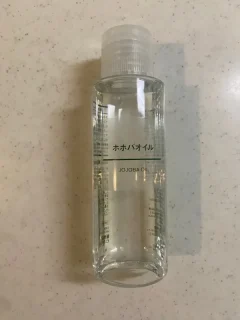


コメントはこちら