クマ被害“過去最多”更新中 神奈川の猟師が植樹で挑む“共生の森”づくり

全国でクマによる人身被害が後を絶たない。2025年度に入っても被害は過去最悪だった2023年度に迫るペースで発生し、死者数はすでに上回る深刻な事態となっている。
対策として捕獲や駆除が強化される一方、神奈川県西部の山北町では、地元の猟師たちが「クマを山へ帰す」ための挑戦を続けている。彼らが未来に託すのは、銃ではなく、ドングリのなる木の苗だ。
過去最悪ペースで続く被害
環境省のまとめによると、2025年度のクマによる人身被害者数は9月末時点で108人に達し、過去最悪のペースで推移している。死者数も10月29日時点で12人となり、統計を取り始めて以降、最悪の数字を更新した(朝日新聞, 東洋経済オンライン調べ)。特に岩手県や秋田県など東北地方で出没件数が急増しており、専門家は警戒を呼びかけている。
被害は山間部だけでなく、市街地や住宅地にも迫っている。自治体が公開する出没マップを見ると、学校から100メートル以内の場所で目撃されるケースも珍しくない。秋はクマが冬眠に備えて食料を求めて活発になる季節であり、例年9月から11月にかけて被害が集中する傾向がある。今年も予断を許さない状況が続いているのだ。
なぜクマは人里に現れるのか
変わりゆく日本の里山
クマの出没増加の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っている。
専門家がまず指摘するのは、人間社会の変化だ。東京農工大学の小池伸介教授は、少子高齢化や都市への人口集中により中山間地域から人が減り、放棄された耕作地が森に戻っていると分析する。これにより、ツキノワグマの分布域はこの40年で約2倍に拡大したという。人とクマの物理的な距離が、かつてなく縮まっているのだ。
それに加え、山の食料不足も大きな要因とされる。特にブナやミズナラなどのドングリ類が不作の年は、クマは餌を求めて人里へ下りてくる。そしてさらに、人里に放置された柿や栗、畑の野菜、さらには生ゴミなどが、クマを強く引き寄せる「誘引物」となっているのだ。
「人を恐れないクマ」の出現
近年、専門家が懸念しているのが「人慣れ」したクマの増加だ。人里で容易に栄養価の高い食べ物を得る経験をすると、クマは人間を恐れなくなる。かつては臆病で人を避けるのが普通だったが、世代を重ねるうちに、人を「脅威ではない存在」と学習する個体が増えている可能性が指摘されている。こうしたクマは、より大胆に人間の生活圏へ侵入し、深刻な被害を引き起こすリスクが高い。
次のページへ:神奈川の挑戦:「クマを山へ帰す」植樹活動







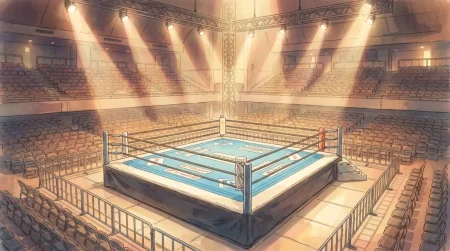






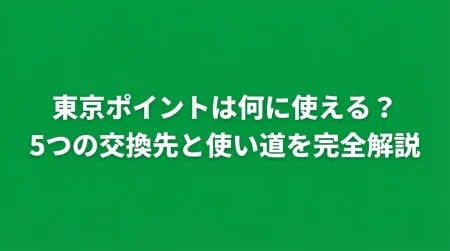




























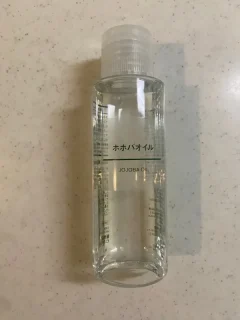



コメントはこちら