児童手当2万円上乗せ案、期待と課題 「支援金より減税を」の声も
「現金給付」か「減税」か 国民が求める支援の形
こうした背景から、今回の「児童手当2万円上乗せ」案に対しても、手放しで歓迎する声ばかりではない。「さらなる現金給付よりも、減税や社会保険料負担の軽減を優先すべきだ」という意見が根強く存在するのである。
支援金制度は、一度徴収した保険料を再分配する仕組みであり、国民にとっては「取られてから配られる」という感覚が否めない。一方で、減税や社会保険料の軽減は、直接的に可処分所得を増やす効果がある。特に、物価高騰が続くなか、日々の生活防衛に追われる多くの世帯にとって、手取り収入の増加はより直接的な支援と受け止められやすい。
「少子化の根本的な原因の一つは、経済的な不安から、若い世代が結婚や出産に踏み切れないことにある。(中略)この制度は、まさにその世代の若者たちの社会保険料負担を増やし、手取り収入を減少させます。」
専門家からは、少子化対策として本当に効果的なのは、これから子どもを持つ可能性のある若者世代への支援であり、彼らの負担を増やしかねない現行の財源確保策は逆効果になりうるとの懸念も示されている。また、児童手当の拡充に伴い、高校生年代の子どもを持つ世帯の扶養控除が縮小されるなど、税制との複雑な兼ね合いも課題となっている。政府は負担増にならないよう制度設計するとしているが、こうした制度の複雑化も、シンプルな減税を求める声につながっている一因かもしれない。
問われる支援の質と今後の焦点
自民党から浮上した児童手当の「2万円上乗せ」案は、子育て世帯へのさらなる経済支援として期待される一方、その財源となる「支援金」制度への国民の不信感という大きな課題を浮き彫りにした。現金給付の拡充は分かりやすい支援策ではあるが、それが国民全体の負担増によって賄われるのであれば、その効果や公平性について慎重な議論が求められる。
今後の焦点は、この上乗せ案が年末の予算編成や税制改正論議の中で、どのように具体化されていくかである。また、関連する扶養控除の扱いがどうなるのかも、子育て世帯の家計に直結する重要なポイントだ。
制度が複雑化するなか、受給対象となる国民は、自ら情報を収集し、必要な申請を忘れずに行うことが不可欠となる。特に2024年の制度改正で新たに対象となった高校生年代の子どもを持つ世帯や、所得制限で対象外だった世帯は、2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分まで遡って受給できるため、注意が必要である。政府や自治体からの情報発信に、引き続き注目していく必要があるだろう。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]

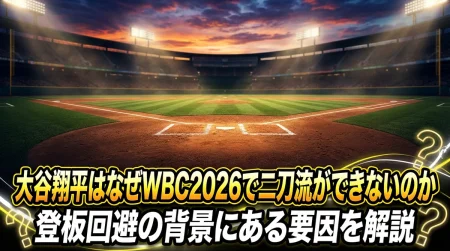







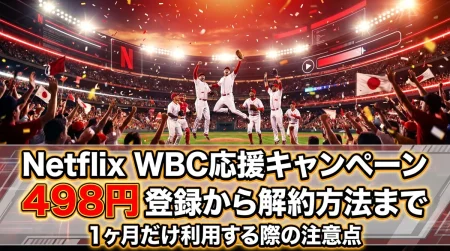










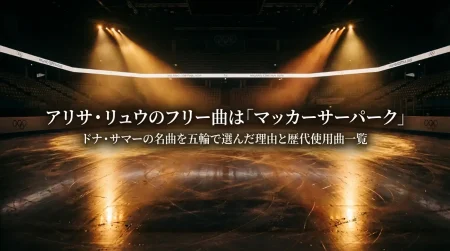
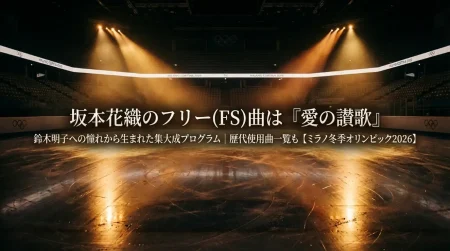
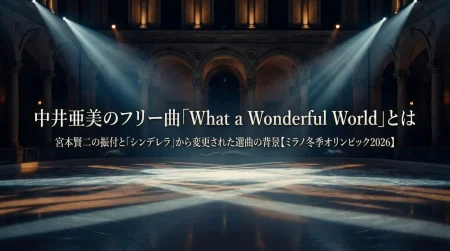



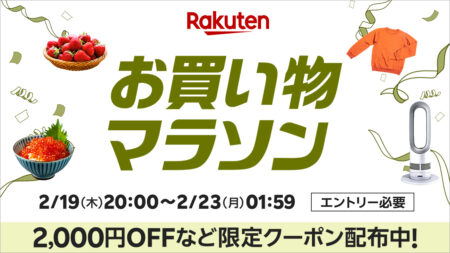


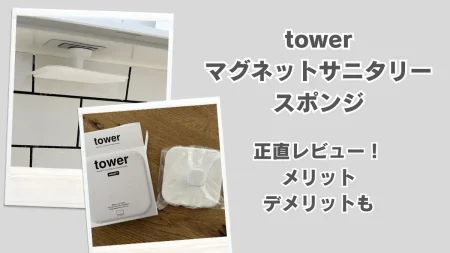
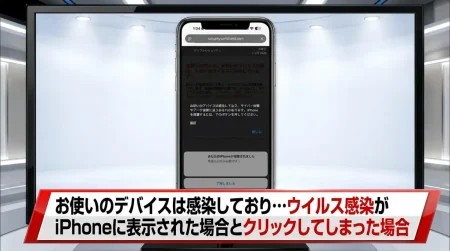

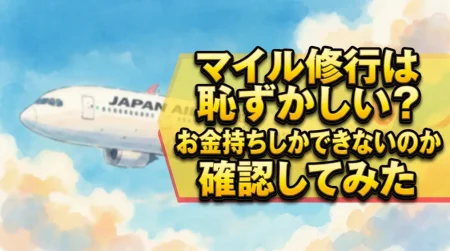
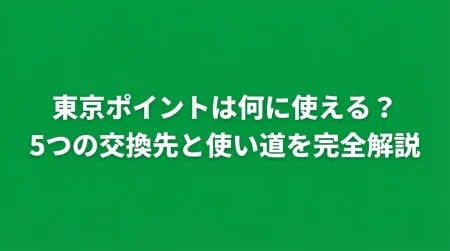

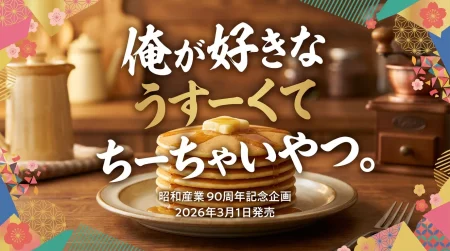






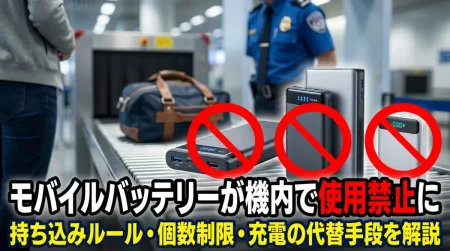














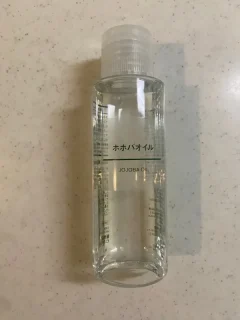

コメントはこちら