児童手当2万円上乗せ案、期待と課題 「支援金より減税を」の声も

時間がない人向けの30秒で理解ゾーン
自民党が経済対策として、児童手当を子ども1人あたり月2万円上乗せする案を検討している。これは2024年10月からの制度拡充に続く動きだが、財源確保のための「子ども・子育て支援金」制度には国民の負担増への懸念が根強い。現金給付の拡充に対し、減税や社会保険料の軽減を求める声も多く、子育て支援のあり方が改めて問われている。
↓ 詳細が気になる方は、このまま下へ ↓
経済対策の新たな一手か、児童手当「2万円上乗せ」案が浮上
2025年11月19日、自民党の小林鷹之政務調査会長は、政府が近く策定する総合経済対策の一環として、児童手当を子ども1人あたり月額2万円上乗せする方向で検討していることを明らかにした。この案では所得制限を設けず、一律に支給する方針が示されている。2024年10月に所得制限撤廃や支給期間延長といった大規模な制度拡充が実施されたばかりの中、さらなる現金給付策が検討の俎上に上がった形だ。
この動きは、深刻化する少子化と物価高騰に直面する子育て世帯への経済的支援を強化する狙いがある。しかし、その財源をどう確保するのか、そしてこの支援策が国民にどう受け止められるのか、早くも議論が始まっている。
2024年「児童手当大改正」の振り返り
今回の「2万円上乗せ」案を理解するには、2024年10月から施行された児童手当の抜本的拡充の内容を把握しておく必要がある。岸田政権が掲げる「異次元の少子化対策」の中核として位置づけられたこの改正は、主に4つの大きな変更点があった。
主な変更点
- 所得制限の撤廃: これまで主たる生計者の所得に応じて給付が減額・停止されていたが、これが撤廃され、全世帯が満額支給の対象となった。
- 支給対象の拡大: 支給期間が「中学校卒業まで」から「高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に延長された。
- 第3子以降の増額: 多子世帯への支援強化として、第3子以降の支給額が年齢にかかわらず月額3万円に倍増した。
- 支給回数の増加: 支払いが年3回(4ヶ月分ごと)から年6回(2ヶ月分ごと)に変更され、家計管理がしやすくなるよう配慮された。
この改正により、子ども1人あたり0歳から18歳までに受け取れる給付総額は、従来の制度に比べ平均で約146万円増加すると試算されている。特に、これまで所得制限で対象外だった高所得世帯や、子どもの多い多子世帯にとって大きな恩恵となる制度変更であった。
表1:児童手当制度の2024年10月からの変更点(月額)
| 区分 | 改正前(~2024年9月) | 改正後(2024年10月~) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(所得に応じて減額・不支給) | 撤廃 |
| 支給対象年齢 | 0歳~中学校卒業まで | 0歳~高校生年代まで |
| 0歳~3歳未満 | 一律 15,000円 | 一律 15,000円 |
| 3歳~高校生年代 (第1子・第2子) | 10,000円(中学生まで) | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円(3歳~小学生) 10,000円(中学生) | 30,000円 |
| 支給回数 | 年3回(4ヶ月ごと) | 年6回(2ヶ月ごと) |
出典:こども家庭庁、厚生労働省等の資料を基に作成
財源確保の仕組みと「支援金」への厳しい視線
一連の子育て支援策拡充で避けて通れないのが財源問題である。政府は、これらの施策の財源として、2026年度から「子ども・子育て支援金」制度を創設する方針を固めている。この制度は、公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されるもので、事実上、社会保険料の負担が増えることを意味する。
負担の対象は、会社員、公務員、自営業者、そして75歳以上の高齢者まで、公的医療保険に加入するほぼ全ての国民に及ぶ。政府の試算では、2028年度には総額1兆円規模となり、加入者1人あたりの平均負担額は月500円弱、年収600万円の会社員の場合は月額1,000円程度になるとされている。
この「支援金」という名の新たな負担に対しては、国民から厳しい視線が注がれている。「税」ではなく社会保険料として徴収する手法に「ステルス増税ではないか」との批判や、子育て世帯以外も広く負担することから「負担と受益が一致しない」との指摘が専門家などから上がっている。実際、複数の世論調査では、この支援金制度に「反対」する声が「賛成」を上回る結果が出ている。
次ページ:「現金給付」か「減税」か 国民が求める支援の形








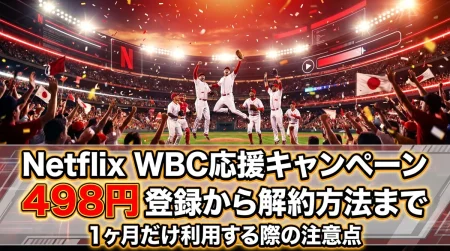










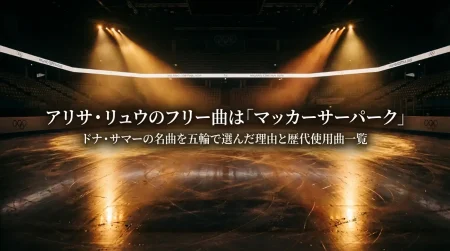
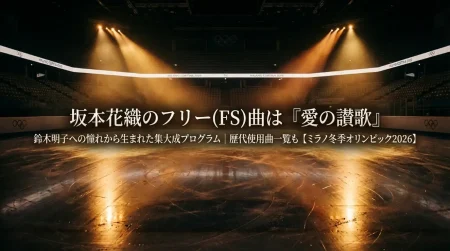
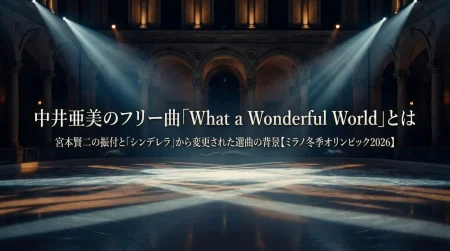




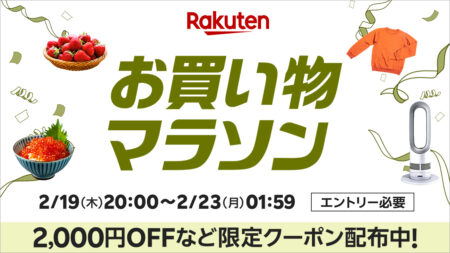


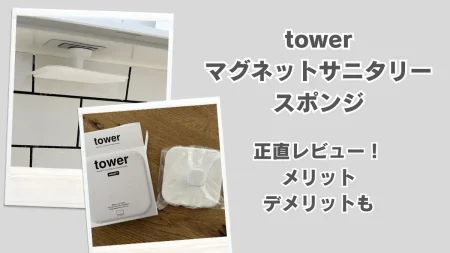
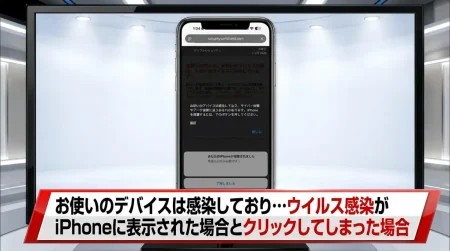

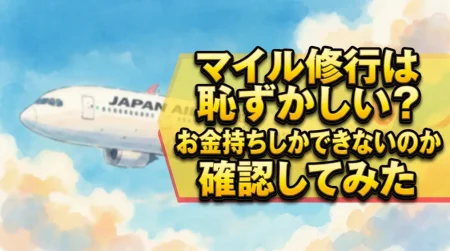
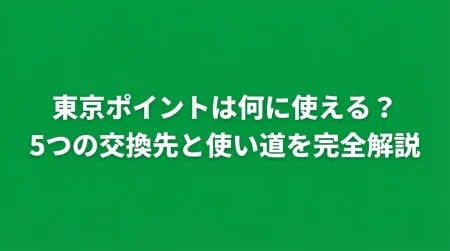

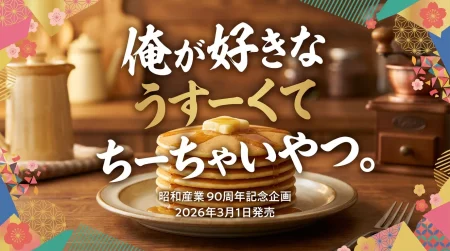






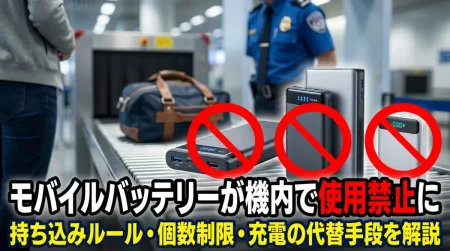














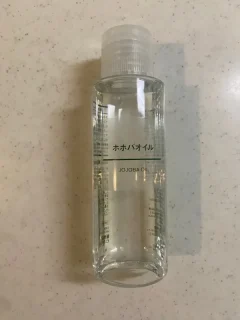

コメントはこちら