フジ清水社長、崖っぷちの船出「この1年が勝負」 巨大組織は本当に変われるか
期待と懐疑の交錯 – 問われる改革の本気度と自浄作用
一連の改革に対し、社内外の視線は期待と懐疑が入り混じる。スポンサーからは「本気度が感じられる」との声が上がる一方、「実行を見守りたい」という慎重な姿勢が多数を占めるのが実情だ。民放連は改革を評価し、清水社長の副会長職復帰を承認したが、これはあくまで「体制が整った」という判断に過ぎない。
SNS上では、実業家の堀江貴文氏と清水社長が大学講義で共演し、堀江氏の番組起用に前向きな姿勢を示したことが「忖度を忘れるメッセージ」として好意的に受け止められる場面もあった。
今回の清水社長と堀江貴文氏の授業は、そうしたフジテレビの改革に対する本気度への懐疑的な見方に対する一石として、大きなインパクトがあると考えられます。特に大きいのはフジテレビ社内に対するメッセージでしょう。
しかし、改革の道のりは平坦ではない。2025年11月7日、改革の象徴として取締役に登用されたばかりの安田美智代氏による不適切な経費精算が発覚し、辞任。清水社長は「これから改革という時に痛恨の思い」と会見で謝罪し、SNSでは「改革の目玉人事がこれか」と失望の声が広がった。一方で、この問題が「強化されたチェック機能によって判明した」という側面もある。改革によって不正が暴かれるという皮肉な結果は、自浄作用が働き始めた証左と見ることもできるかもしれない。
(動画:安田取締役辞任に関する清水社長の会見 ANN/テレ朝)
フジテレビの未来はどこへ – 信頼回復と成長戦略、正念場の一年
清水社長が断行する改革は、ガバナンス、組織文化、事業戦略という広範にわたる、まさに「聖域なき改革」だ。しかし、新役員の不祥事は、根深い体質改善の難しさを改めて浮き彫りにした。改革プランという「設計図」はできた。だが、それを巨大組織の隅々まで浸透させ、実行できるかが最大の課題である。
「人権を尊重する会社」への再生による信頼回復と、「コンテンツカンパニー」への進化による成長戦略。この二つの目標を両立させる困難な舵取りが、清水社長には求められている。「この1年間が勝負」という言葉の重みは増すばかりだ。フジテレビが真に生まれ変われるのか、社会全体がその動向を固唾をのんで見守っている。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]





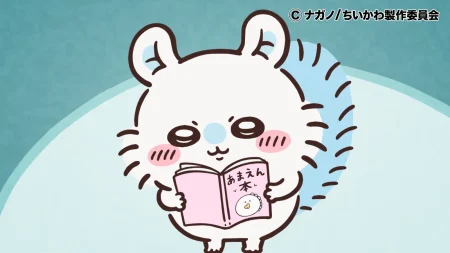

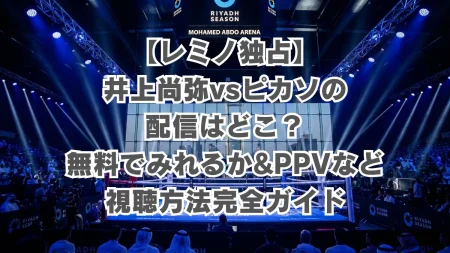
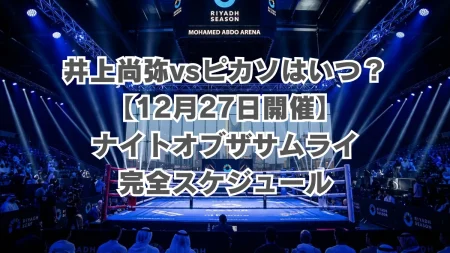

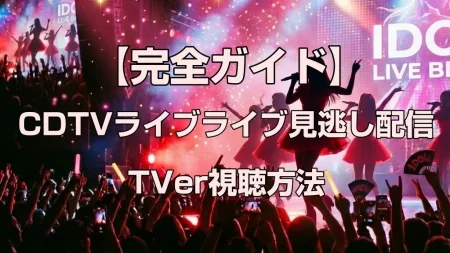































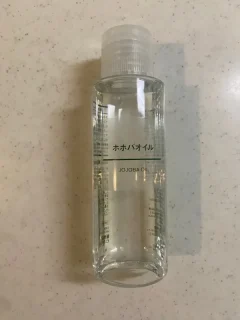






コメントはこちら