クマ被害“過去最多”更新中 神奈川の猟師が植樹で挑む“共生の森”づくり
神奈川の挑戦:「クマを山へ帰す」植樹活動
こうした状況に対し、神奈川県山北町の猟師たちが始めたのが、広葉樹の植樹活動だ。発案者の一人である杉本一さん(87)は、「クマだって人間を避けて生きたいんだ」と語る。
彼らの目的は、クマの餌となるブナやクルミ、クヌギなどの木を山奥に植え、クマが人里に下りてこなくても生きていける豊かな森を取り戻すことにある。
「このままでは神奈川でも絶対に被害は避けられない。対策を急がなければ」― 杉本一さん
この活動の背景には、戦後の拡大造林政策で日本の山の多くがスギやヒノキといった針葉樹の人工林に変わってしまったことへの問題意識がある。針葉樹林はクマなどの野生動物にとって、食料が乏しい「緑の砂漠」に等しい。
杉本さんらは、この生態系のバランスを少しでも元に戻そうと、10年以上前から地道にドングリを拾い、苗木を育ててきた。
活動は狩猟仲間で作る「豊猟会」などに引き継がれ、2025年3月にはボランティア約80人が集まり、クヌギやクルミの苗木約1500本を植樹した。これは、目先の被害対策だけでなく、数十年先を見据えた、自然との共生を目指す試みだ。
多様な視点と社会の反応
共感と支持の声
この猟師たちの活動はメディアで報じられると、X(旧Twitter)などのSNSで大きな反響を呼んだ。「クマだけを悪者にするのは違う」「原因を作った人間側が行動するのは素晴らしい」といった肯定的な意見が多く見られ、多くの人々が共感を示している。駆除一辺倒ではないアプローチに、新たな希望を見出す声が広がっている。
懐疑的な見方と現実的な課題
一方で、この活動だけで問題が解決するのかという懐疑的な声も存在する。「植樹の効果が出るまでには何十年もかかる。それまでの安全はどう確保するのか」という現実的な指摘は重い。自然写真家の永幡嘉之氏は「野生動物を相手に共存はありえない」と述べ、安易な共存論に警鐘を鳴らす。
また、世論は複雑だ。Yahoo!ニュースが行った意識調査では、「クマの出没に対する安全対策」として「捕獲・駆除を強化する」と答えた人が約90%に上った。理想としての共存と、現実の恐怖との間で、社会の意見は揺れ動いている。
共存への道は一つではない
専門家は、クマとの共存に「特効薬」はないと口をそろえる。山北町の植樹活動は、問題の根本原因に目を向けた重要な一歩だが、それだけですべてが解決するわけではない。被害を防ぐためには、複数の対策を組み合わせることが不可欠だ。
具体的には、人里の誘引物を徹底的に除去する「環境管理」、電気柵などで物理的に侵入を防ぐ「防除」、そして危険な個体を適切に管理する「個体数管理」など、地域の実情に合わせた総合的な対策が求められる。これは、人とクマの生活圏を明確に分ける「ゾーニング(棲み分け)」という考え方につながる。
神奈川の猟師たちが植えた一本一本の苗木は、すぐにクマの空腹を満たすことはできないかもしれない。しかし、その行動は「なぜクマは山から下りてくるのか」という根源的な問いを社会に投げかけている。
駆除か、共生か。単純な二元論では語れないこの問題に対し、彼らの挑戦は、私たちが未来に向けてどのような関係を自然と築いていくべきか、考えるきっかけを与えてくれる。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]








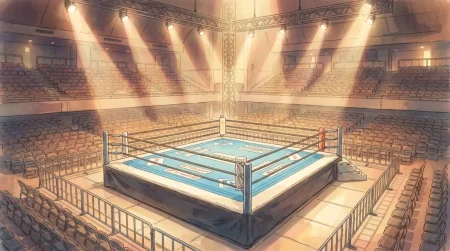






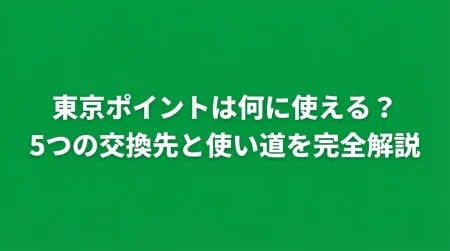



























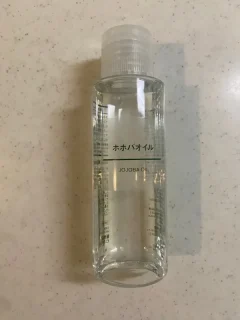


コメントはこちら