大正ロマンを感じる函館散歩。二十間坂の麓に立つ「日本最古のコンクリート電柱」訪問記

函館といえば、美しい夜景や新鮮な海の幸、異国情緒あふれる街並みを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、この街にはもっとディープな、知る人ぞ知る魅力的なスポットがあるんです。それが、なんと100年以上も現役で街を支え続けている「日本最古のコンクリート電柱」です!
「え、電柱…?」と思ったそこのあなた。私も最初はそうでした。でも、実際にこの目で見てみると、ただの電柱ではない、歴史の重みと物語が詰まった素晴らしいランドマークだったんです。今回は、私が実際に訪れて感じた感動と、その魅力をたっぷりお伝えします!
100年以上も現役!「日本最古のコンクリート電柱」とは?
まず基本情報から。この電柱は、函館市末広町の赤レンガ倉庫群や元町エリアに近い場所にあります。建てられたのは、なんと大正12年(1923年)10月。当時の函館水電会社(現在の北海道電力ネットワークの前身の一つ)によって設置されました。2023年には建立100周年を迎えた、まさに「生きた歴史遺産」なんです。
高さは約10メートル。一般的な円柱形ではなく、上に向かって細くなる「四角い角錐形」をしているのが最大の特徴です。これは当時、現場で型枠を組んでコンクリートを流し込む「現場打ち工法」で作られたためだそう。
コンクリートの耐用年数は一般的に50〜60年と言われる中、100年以上も現役で使われているなんて、驚きですよね。大正、昭和、平成、そして令和と、4つの時代を越えて函館の街を見守り続けてきたのです。
実際に見てきた!私の体験レビュー
アクセスと周辺の雰囲気
私が訪れたのは、秋晴れの10月23日お昼前。函館市電の「十字街」電停から歩いて7〜8分ほどで、目的の場所に到着しました。有名な観光スポット「二十間坂」のすぐ麓にあり、大きな案内看板も設置されているので、迷うことはありませんでした。

周辺は、金森赤レンガ倉庫群にも近く、観光客で賑わうエリア。私が訪れたときも、5組ほどの観光客が電柱を眺めたり、熱心に写真を撮ったりしていました。少し撮影の順番を待つことはありましたが、混雑して見られないということはなく、じっくりと観察できました。
すぐ横には、街路樹が美しく色づいた「開港通り」が伸びていて、歴史的な電柱とのコントラストがとても綺麗でしたよ。

初めて見る「四角い電柱」の衝撃
そして、いよいよご対面。人生で初めて見る「四角い電柱」に、思わず「おぉ…」と声が漏れてしまいました。見慣れた丸い電柱とは全く違う、角張った無骨なフォルム。それでいて、どこかモダンな雰囲気も感じさせます。

表面をよく見ると、長い年月を経てきたことがわかる風合いがあり、これが100年以上前に造られたものだなんて信じられないほど、しっかりとした佇まいでした。そして何より、今も電線を支え、私たちの生活に電気を送り届けている「現役」であるという事実に、二度驚かされました。
なぜここに?歴史を知るともっと面白い!
火災と景観が生んだ「特別な電柱」
では、なぜ当時主流だった木製の円柱ではなく、珍しいコンクリート製の四角い電柱が建てられたのでしょうか。その背景には、函館ならではの理由がありました。
一つは、度重なる大火への対策です。海風が強く、木造家屋が多かった函館は、昔から火災が多い街でした。そのため、燃えにくいコンクリートを使った耐火建築への関心が高まっていたのです。この電柱も、その流れの中で生まれた防火意識の象徴だったのですね。
もう一つの理由は、景観への配慮。この電柱が建てられたのは、近くにあった「北海道拓殖銀行函館支店」が鉄筋コンクリート造りで新築された際のこと。そのモダンな建物とのデザインの調和を図るため、銀行が資金を提供して特別に造られたものだと言われています。街の景観を大切にする函館らしいエピソードです。

市民に愛された「夫婦電柱」の物語
実はこの電柱には、心温まる愛称がありました。建設後、建物を挟んで向かい側にもう一本同じ形の電柱が建てられ、二本合わせて「夫婦(めおと)電柱」と呼ばれ、市民に親しまれていたそうです。
残念ながら、もう一本の電柱は昭和46年(1971年)の道路工事で一度撤去されてしまいました。しかし、平成に入ってからその場所に同形の電柱が再建され、今も「夫婦」のように並んで立っています。訪れた際は、ぜひ新旧二本の電柱を見比べてみてください。過ごしてきた年月の違いが、色や質感からはっきりと感じ取れて興味深いですよ。

次ページ:よかった点と注意点







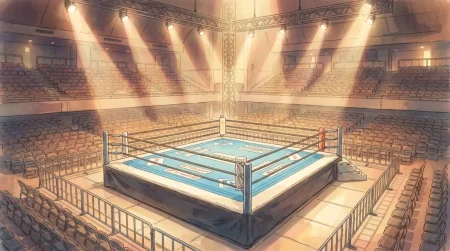






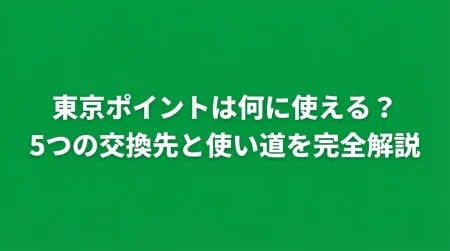




























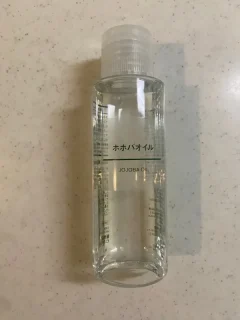



コメントはこちら