パワースポットの風格!諏訪大社・本宮の見どころやご利益を現地レポ!参拝の感想と巡り方

日本最古の神社の一つとして知られる、長野県の諏訪大社。その中心的な存在である「上社本宮(かみしゃほんみや)」へ、先日、資格試験の合格を祈願するために行ってきました。
諏訪大社といえば、諏訪湖を囲むように鎮座する四つのお社(上社本宮・前宮、下社秋宮・春宮)を巡る「四社まいり」が有名です。私も以前にすべて巡った経験があるのですが、今回はあえて本宮だけに絞って参拝することに。
なぜなら、四社の中でも最大の規模と格式を誇り、見どころが凝縮されているのが、この本宮だからです。実際に訪れてみると、その荘厳な雰囲気と、自然と歴史が織りなす独特の空気に圧倒されました。この記事では、私が体験した本宮のリアルな魅力と、これから訪れる方が知っておきたいポイントを、写真のイメージと共にお届けします!
諏訪大社「上社本宮」ってどんなところ?
四社からなる日本最古級の神社
諏訪大社は、長野県の諏訪湖周辺に4つの境内地をもつ神社です。公式ウェブサイトによると、その歴史は非常に古く、『古事記』の国譲り神話にまで遡るとされ、国内にある最も古い神社の一つとされています。諏訪湖の南側に「上社(かみしゃ)」、北側に「下社(しもしゃ)」があり、さらに上社は本宮と前宮、下社は秋宮と春宮に分かれています。
本宮ならではの特徴とご利益
今回訪れた上社本宮は、その四社の中心的な存在。御祭神は建御名方神(タケミナカタノカミ)で、古くから風と水を司る龍神としての神徳や、武勇の神として信仰されてきました。現在では生命の根源、生活の源を守る神として広く崇敬されています。
本宮の最も大きな特徴は、多くの神社にある「本殿」が存在しないことです。代わりに、背後にそびえる守屋山そのものを御神体として拝むという、古代の自然崇拝の形が今も色濃く残っているのです。この独特の様式は「諏訪造り」と呼ばれ、建築様式としても非常に価値が高いものとされています。
平日午前中の本宮へ!リアルな参拝体験記(2025年10月21日)
広大な駐車場から始まる参道散策
私が訪れたのは、10月下旬の平日の午前10時頃。資格試験の合格を祈願するため、車で向かいました。本宮は観光の拠点にもなっているため、広々とした無料駐車場が完備されているのが嬉しいポイントです。観光バスもここに停車するので、アクセスの良さは抜群ですね。


駐車場から参道に入ると、お土産屋さんや飲食店が軒を連ね、散策するだけでも楽しい雰囲気。平日だったためか、まだ人影はまばらで、ゆっくりと自分のペースで進むことができました。

大きな鳥居をくぐる手前には、清潔なお手洗いも完備されています。四社巡りの休憩スポットとしても最適だと感じました。

境内へ。歴史とパワーを感じるスポットたち
鳥居をくぐり、まずは手水舎で心身を清めます。作法がわからなくても、周りの方を見習ったり、最近では神社の公式サイトで動画解説があったりするので安心です。(最後に作法動画あり!行く前に要チェック!)

参道を進むと、まず目に飛び込んでくるのが、信州出身の伝説的な力士「雷電為右衛門」の像です。諏訪の神様は力の神としても知られ、相撲と縁が深いのだとか。その堂々たる姿は、まさにパワースポットの入り口にふさわしい迫力でした。

境内には高島神社など、いくつかの末社も鎮座しています。一つひとつ丁寧にお参りしながら、石段を上っていきます。

石段を上りきると、歴史を感じさせる「塀重門」が見えてきます。ここから先は、さらに神聖な空気が漂うエリアです。

門をくぐると、勅願殿や宝物殿、社務所などが並んでいます。宝物殿には、諏訪大社ゆかりの貴重な品々が展示されており、歴史好きにはたまらない空間です(拝観は有料)。



荘厳な幣拝殿と、心静まる時間
そして、いよいよ参拝の中心である「幣拝殿(へいはいでん)」へ。残念ながら、一般の参拝者は幣拝殿のすぐ近くまでは入れませんが、その距離感がかえって厳かな雰囲気を高めています。朱色などの鮮やかな彩色はなく、木材そのものの色と質感を活かした素朴ながらも重厚な造りは、まさに圧巻の一言。

左右片拝殿

左右片拝殿
周囲を深い森に囲まれ、聞こえるのは風の音と鳥の声だけ。静寂の中で手を合わせていると、日々の喧騒を忘れ、心がすーっと澄んでいくのを感じました。これぞパワースポットの醍醐味ですね。無事に試験に合格できるよう、心を込めて祈願しました。
次ページ:本宮参拝のメリット・デメリット








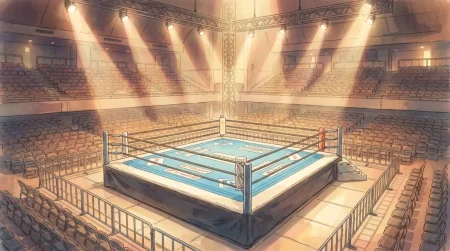






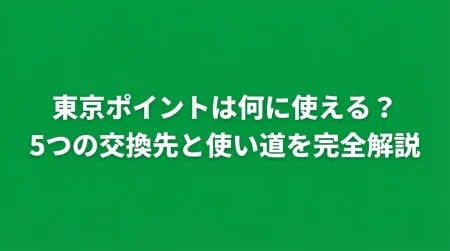



























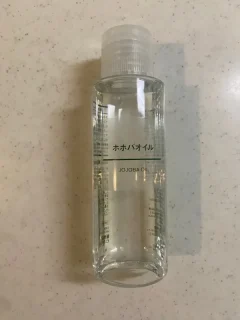


コメントはこちら