【若者が悲鳴】給料から天引きされる社会保険料、なぜ上がり続ける?スウェーデン「高負担でも納得」決定的な違い

給与明細を見るたびに、手取り額の伸び悩みを感じる人は少なくないだろう。その大きな要因の一つが、静かに、しかし確実に増え続ける社会保険料だ。物価高に賃金上昇が追いつかない中、この「見えざる負担」は家計を圧迫し続けている。なぜ日本の社会保険料は上がり続けるのか。そして、同じく高負担でありながら国民の不満が少ないとされるスウェーデンとは、一体何が違うのだろうか。その構造的な違いを、事実に基づいてひもとく。
なぜ日本の社会保険料は上がり続けるのか
社会保険料の上昇は、個人の努力ではどうにもならない、日本社会が抱える構造的な課題だ。
避けられない「少子高齢化」という構造
最大の理由は、世界でも類を見ないスピードで進む「少子高齢化」である。日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は、1995年の14.6%から2023年には29%を超え、ほぼ倍増した。高齢者が増えれば、医療や介護にかかる費用(社会保障給付費)は必然的に膨らむ。一方で、保険料を支払う現役世代の人口は減少の一途をたどっている。少ない人数で、増え続ける巨大なコストを支えなければならない。これが、一人当たりの負担が増え続ける根本的な構図だ。
給与明細から見る「見えにくい」負担増
この負担増は、私たちの家計に直接影響を与えている。ある調査によれば、2000年から2022年にかけて勤労者世帯の年収が約1.1倍にしか増えていないのに対し、社会保険料は約1.4倍に増加した。給与から天引きされるため税金ほど意識されにくいが、着実に可処分所得を蝕んでいるのだ。
さらに、私たちが支払う健康保険料の約4割は、75歳以上の高齢者の医療費を支えるための「後期高齢者支援金」などに充てられている。これは、いわば現役世代から高齢者世代への「仕送り」のような仕組みであり、この仕送り額が年々増加していることが、保険料率を押し上げる直接的な原因となっている。
なぜスウェーデンは「高負担」に不満が少ないのか
ここで視点を変え、高福祉・高負担国家の代表格であるスウェーデンを見てみよう。消費税率25%など、日本よりもはるかに負担は重いが、国民の不満は驚くほど少ないと言われる。その背景には、日本とは決定的に異なる哲学が存在する。
鍵は「受益と負担の見える化」
スウェーデンで高負担が受け入れられている最大の理由は、支払った税金や保険料が、自分たちの生活にどう還元されているかが明確に「見える」ことにある。政府の財政運営の透明性が高く、国民は「支払った分、質の高い公共サービスをきちんと受けている」という強い実感、つまり「納得感」を持っているのだ。
「現役世代」も主役の社会保障
日本との最も大きな違いは、社会保障の恩恵を受ける対象にある。日本の社会保障が年金や高齢者医療など、主に引退後の世代に向けられているという印象が強いのに対し、スウェーデンでは社会保障費の約半分が「現役世代」のために使われる。
具体的には、大学までの教育費無償化、安価な保育サービス、手厚い育児休業手当、充実した失業保険や職業訓練などだ。子育てやキャリア形成の各段階で、誰もが制度の恩恵を直接的に受けることができる。これにより、現役世代も社会保障を「自分たちのための制度」として捉え、その維持のために高い負担をすることも当然と考える文化が根付いている。
次ページ:専門家の視点と今後の展望











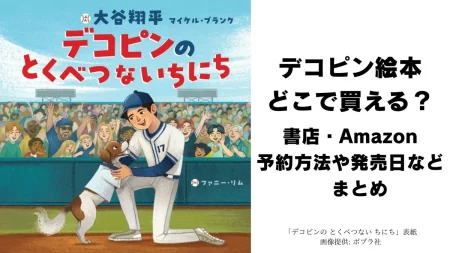




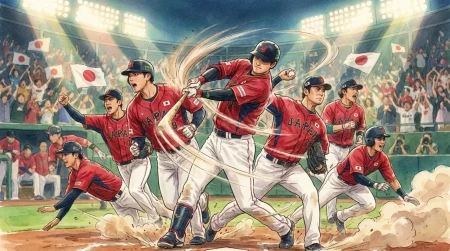





















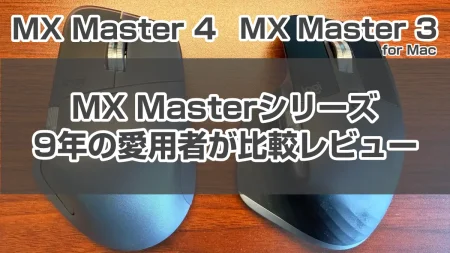




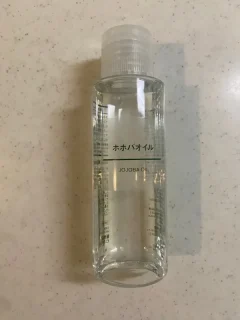






コメントはこちら