【上野の穴場】寛永寺・清水観音堂は東京の清水寺?歴史と見どころを体験レビュー

取材・編集:MEDIA DOGS 編集部/ © 2025 MEDIA DOGS
都会の喧騒を忘れる、江戸情緒あふれる空間
上野公園といえば、動物園や美術館を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その一角に、まるで京都に迷い込んだかのような美しいお堂が静かに佇んでいるのをご存知でしょうか?
それが、今回訪れた国指定重要文化財「清水観音堂(きよみずかんのんどう)」です。実際に足を運んでみると、そこは都会の喧騒を忘れさせてくれる、歴史と自然が調和した心安らぐ空間でした。
この記事では、私が体験して感じた清水観音堂の魅力を、歴史や見どころを交えながらたっぷりとお届けします。
清水観音堂とは?基本情報をサクッと解説
まずは、清水観音堂がどのような場所なのか、基本的な情報から見ていきましょう。

京都・清水寺を模したお堂
清水観音堂は、江戸時代初期の寛永8年(1631年)に、徳川家康の側近であった天海大僧正によって建立されました。

400年の歴史があると考えるとロマンを感じます
公式ホームページによると、江戸城の鬼門(北東)を守るために創建された「東叡山 寛永寺」を構成するお堂の一つです。
その名の通り、京都の有名な清水寺を模して造られており、不忍池を見下ろす高台にせり出すように建てられた「舞台造り」が特徴。
江戸にいながら京都の名所の雰囲気を味わえるように、という天海僧正の粋な計らいが感じられますね。
上野公園に現存する最古の建造物
驚くべきことに、この清水観音堂は、創建時期が明確な建造物としては上野の山に現存する中で最も古いと言われています。
もともとは別の場所(現在の東京文化会館の西側あたり)にありましたが、元禄7年(1694年)に現在の場所へ移築されました。数々の戦火や災害を乗り越え、約400年前の姿を今に伝える貴重な国指定重要文化財なのです。
次のページへ:【体験レビュー】実際に訪れてわかった5つの見どころ











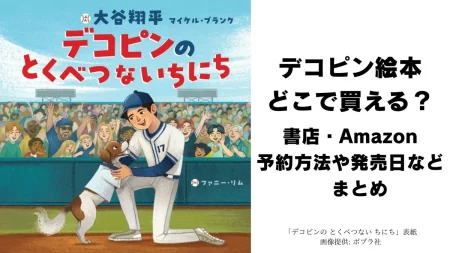




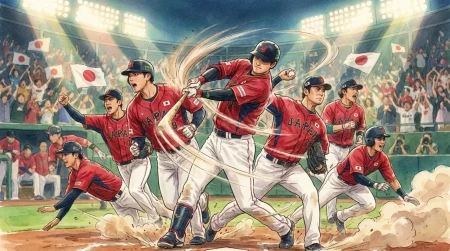





















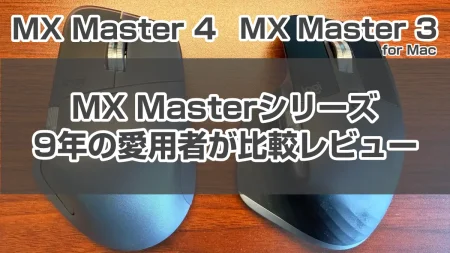




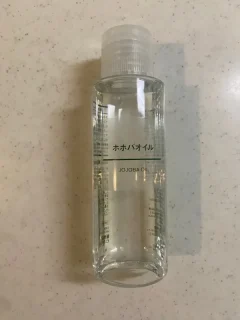






コメントはこちら