「売らない店」b8ta、日本から全店舗撤退。体験型ストアの挑戦、5年で閉幕
撤退の背景、理想と現実のギャップ
華々しく登場したb8taだが、その道のりは平坦ではなかった。撤退の予兆は、実は数年前から現れていた。
先行した米本国の事業停止
衝撃が走ったのは2022年2月。米国のb8ta本社が、新型コロナウイルスの影響による客足の減少や、地主との交渉不調などを理由に、米国内の全店舗を閉鎖し、事実上事業を停止したのだ。 これを受け、日本法人のベータ・ジャパンはライセンス契約を結ぶ形で独立し、独自の道を歩み始めた。しかし、いわば生みの親を失った状態での船出は、決して楽なものではなかった。
日本での苦戦と構造的課題
日本法人は当初、2025年までに最大10店舗体制を目指すとしていたが、計画は未達に終わった。 2025年3月には有楽町店と大阪・梅田店を閉店。そして今回の渋谷店の閉店で、ついに国内店舗はゼロとなる。撤退の背景には、都心一等地という立地がもたらす高額な賃料や人件費といった高コスト構造と、出店企業側が求める短期的な売上とのミスマッチがあったと指摘されている。 「体験」という長期的なブランド価値の構築を目的とするb8taのモデルと、短期的な販売成果を重視せざるを得ない企業の現実との間には、埋めがたい溝があったのかもしれない。
世間の反応と、b8taが残したもの
突然の撤退発表に、SNSでは驚きと惜しむ声が広がった。あるユーザーは「いつも通勤途中に見かけていたけど、、、」と日常の風景が失われることを寂しげに投稿。また、別のユーザーは「ある種、見るだけのお店にお金は払わないという答えは出たように思います」と、ビジネスモデルの難しさを冷静に分析する声も上がった。
事業としては幕を閉じるが、b8taが小売業界に残した功績は決して小さくない。オンラインでは伝えきれない商品の魅力を五感で伝える「体験価値」の重要性を改めて提示し、多くの企業にリアル店舗の新たな可能性を示唆した。その思想は、他の百貨店が手がける「売らない売り場」などにも影響を与えている。b8taの挑戦は失敗に終わったのかもしれない。しかし、それは同時に、小売りの未来を考える上で避けては通れない、価値ある「実験」だったのである。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]











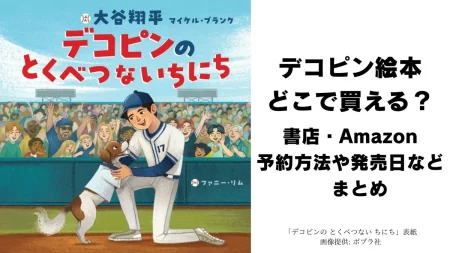




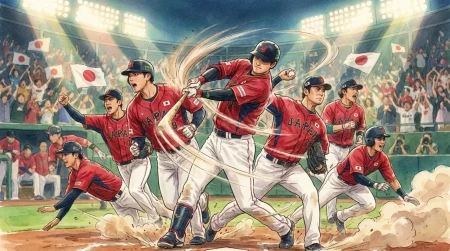





















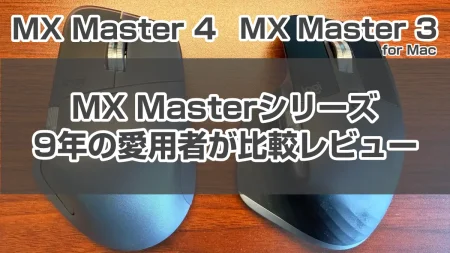




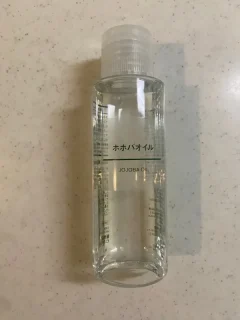






コメントはこちら